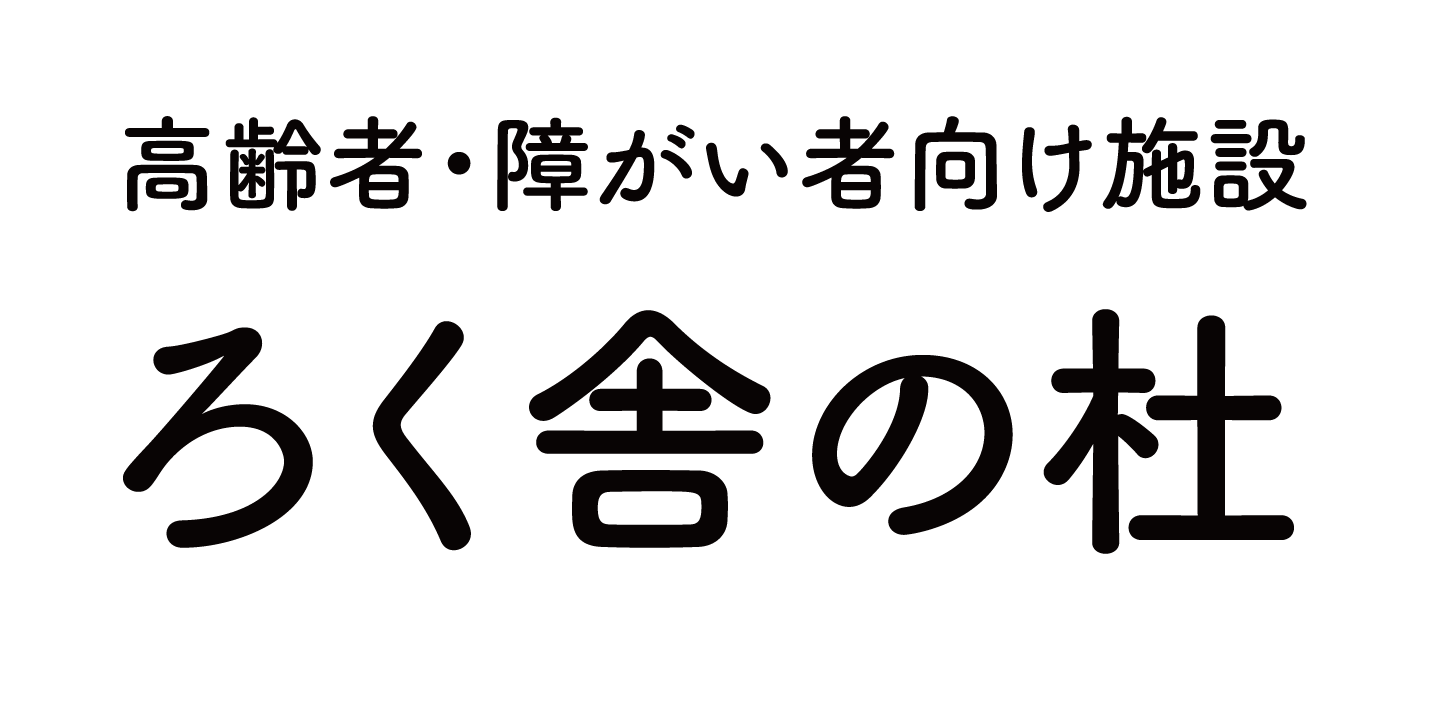現場で学ぶ口腔ケアの実践 ~実習の1日を振り返って~
こんにちは、社会福祉法人ろく舎です!
先日お伝えした北海道大学歯学部の学生さんによる実習プロジェクト。今回は、実際の実習の様子をお届けします。未来の歯科医師たちが、高齢者の口腔ケアについてどのように学んだのか、その一日をレポートします!
実習の一日をのぞいてみました

朝8時半、実習スタートです。最初に当法人の理念や特長、高齢者ケアについての座学の時間を設けました。福祉施設での実習は初めてという学生さんがほとんどだったため、まずは介護福祉の現場について理解を深めていただくことからプログラムを組み立てました。
トレーニングルームでの交流



座学の後は、 3Fトレーニングルームへ移動。学生さんたちには、まず機能訓練の器具を体験していただくことで、高齢者の方々が日々取り組んでいるリハビリの重要性を実感してもらいました。
利用者様と学生さんの交流は、私たちの想像以上に自然な形で深まりました。若い学生さんの訪問に、利用者様も普段とは違う表情で応じられる場面が印象的でした。この交流は、普段の生活に新しい刺激をもたらし、利用者様の意欲向上にもつながったと感じています。
食事の様子と口腔ケア


お昼の時間には、利用者様の食事の様子を見学。姿勢や食材の形状、咀嚼・嚥下の状態など、教科書では学べない実際の高齢者の食事について観察してもらえる時間になったと思います。
食後は日常的な口腔ケアの手順や工夫、声かけの方法など、実践的な技術を実際に見ていただきました。
この時間は、私たち職員にとっても、普段当たり前に行っている業務を見つめ直す良い機会となりました。学生さんからの新鮮な視点での質問が、私たちの気づきにもつながったことは大きな収穫でした。
学生考案!口腔機能向上レクリエーション


学生さんたちに口腔機能向上のためのレクリエーションを企画してもらい、利用者様と一緒に実践していただきました。8週間の実習期間を通して、各グループがそれぞれ創意工夫を凝らしたゲームを実施し、施設内に笑顔があふれる時間となりました!


共通していたのは「楽しみながらも口腔機能のトレーニングになる」という目的と、多くのゲームでストローが活用されていたこと。ストローを使うことで、自然に口周りの筋肉を使い、また肺活量の向上にも繋がるー。
回ごとに違った楽しみ方・盛り上がりがあり、どれも素晴らしい考案のゲームでした。その中でも、北海道らしさが感じられる「カーリング」や、季節にちなんだ「豆移し競争」など、色々な視点から利用者様が興味を持てるような工夫が施されており、感心いたしました!
実習を通しての気づきと成果


実習の最後には振り返りの時間を設け、意見交換を行いました。
この8週間の実習受け入れを通じて、私たちの施設とスタッフ、そして利用者様にとって多くの気づきと成果がありました。
まず何より、若い学生さんとの交流が利用者様の生活に新たな刺激をもたらしたことが大きな成果でした。普段とは違う話題や活動に触れることで、利用者様の表情も明るくなり、日常に彩りが加わった期間となりました。
私たちスタッフにとっても、専門的な視点からの質問や観察は、日々の業務を見つめ直す貴重な機会となり、特に口腔ケアと全身の健康との関連性への認識が深まり、ケアの質向上への意識が高まりました。
さらに、外部との連携によって、施設全体に新しい風が吹き込まれたことも大きな収穫でした。異なる視点や専門性との交流は、私たちの施設の活性化につながり、スタッフの意欲向上にも寄与しました。
今後の展望
8週間にわたる実習受け入れを終えて、当法人では今後もこのような教育機関との連携を継続・発展させていきたいと考えています。若い世代の歯科医療者との交流は、私たちの施設にとっても、利用者様にとっても大変有意義なものでした。
未来の歯科医療を担う若者たちと私たちの施設との貴重な連携。
次回は、この素晴らしい連携がどのように生まれたのかという「ご縁」の物語をお届けします。
どうぞお楽しみに!